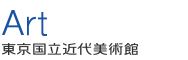2007年2月6日(火)~3月31日(土)
協力:日本映画撮影監督協会
開映後の入場はできません。
定員=310名(各回入替制)
発券=2階受付
料金=一般500円/高校・大学生・シニア300円/小・中学生100円/障害者(付添者は原則1名まで)は無料
・観覧券は当日・当該回にのみ有効です。
・発券・開場は開映の30分前から行い、定員に達し次第締切となります。
・学生、シニア(65歳以上)、障害者の方は、証明できるものをご提示ください。
・発券は各回1名につき1枚のみです。
★2-3月の休館日:月曜日
映画作品とは、監督や俳優ばかりではなく、数多くのスタッフの創意が組み合わされて完成するものです。中でも映画作りに貢献するスタッフとして、キャメラとフィルムを用いて世界をさまざまな“フレーム”に造形し、映画作品というもう一つの“世界”に向けて素材を生み出す撮影監督の存在を忘れることはできません。撮影機の操作はもちろん、レンズやフィルムの選択、美術監督や照明技師との連繋、フレームや構図の決定、画調のコントロールなど、その複雑な仕事はいずれも映画の根幹に関わるものです。また監督の構想を具体的に実現するため、撮影現場の実務的なリーダーとして活躍するのもキャメラマンの重要な役割です。
その撮影監督の仕事を顕彰すべく2004年にスタートした上映企画がこの「シリーズ・日本の撮影監督」です。今回はその第2期として、日本の無声映画後期にデビューし、その後の日本映画の発展と繁栄に貢献した撮影監督18名の作品を取り上げます。松竹、日活、P.C.L.(東宝)など戦前の指導的な映画会社に集い、戦後には映画の大型化、カラー化の波にも寄り添いながら技術と美を競った“光の魔術師”たちの仕事を追うことで、日本映画への新たな視点を獲得していただければ幸いです。
■(撮)=撮影 (監)=監督・演出 (原)=原作・原案 (脚)=脚本・脚色・シナリオ (美)=美術・装置・美術監督 (音)=音楽・音楽監督 (出)=出演 (構)=構成 (編)=編集 (解)=解説
■本特集には不完全なプリントが含まれています。
■記載した上映分数は、当日のものと多少異なることがあります。
★監督紹介
---------------------------------------------------
河崎喜久三 Kikuzo Kawasaki 1899-1979
1919年に日活京都撮影所に入社。その後マキノプロ、東亜キネマを経てフランスに赴き、ルネ・クレール作品の撮影技師ジョルジュ・ペリナールと親交を持つ。帰国後はJ.O.スタジオ(後に東宝京都)に移籍し、戦後は新東宝で活躍した。新東宝では中川信夫監督、並木鏡太郎監督らの手がける時代劇に定評があったが、1961年の同社の製作中止とともに映画から退いた。
作品1-3撮影
---------------------------------------------------
立花幹也 Mikiya Tachibana 1906-1946
本名は光三郎。帝国キネマ芦屋撮影所で撮影の腕を磨き、その後東京に移って1933年設立の写真科学研究所(P.C.L.)に草創期から在籍、初期P.C.L.の明朗な路線を撮影面で支えた。後に『兄いもうと』(1936年)や『からゆきさん』(1937年)といった木村荘十二監督の佳作、成瀬巳喜男監督の野心作『雪崩』(1937年)などに携わったが、終戦後間もなく逝去した。
作品4-5撮影
---------------------------------------------------
円谷英二(英一) Eiji (Eiichi) Tsuburaya 1901-1970
1919年に天活日暮里撮影所に入社、枝正義郎、杉山公平に師事する。松竹下加茂作品『稚児の剣法』(1927年)で林長二郎(長谷川一夫)と同時デビュー、その後数多くの時代劇を撮影した。1938年、東宝に移籍してから特殊撮影の研究を開始、戦時中の航空映画や戦後の怪獣映画などに貢献し、日本の特撮技術のパイオニアとして不動の地位を築いた。
作品6-7撮影
---------------------------------------------------
三木滋人(稔) Shigeto (Minoru) Miki 1902-1968
1916年にM・パテー商会に入社、吉本啓造、玉井昇に師事する。1921年に東亜キネマ甲陽撮影所に転じ、マキノプロ、新興キネマ京都を経て第一映画社で溝口健二監督の傑作『浪華悲歌』や『祇園の姉妹』(いずれも1936年)を担当して名声を確立。その後松竹下加茂で技術部長に任じられ、戦後は東映京都撮影所の時代劇を中心的に支えた。本名は稔だが1938年頃から滋人を名乗る。
作品8-10撮影
---------------------------------------------------
石本秀雄 Hideo Ishimoto 1906-1967
1923年、マキノプロに入社して河崎喜久三に師事する。1927年に一本立ちした翌年に片岡千恵蔵プロに移籍、稲垣浩監督らの打ち出した明朗時代劇の路線を支えた。1937年日活へ移籍、稲垣やマキノ正博らの名監督に信頼されて日活の代表的な撮影技師の一人となったが、とりわけ伊藤大輔とは、戦後に松竹京都撮影所に移ってからも『大江戸五人男』(1951年)など多くの秀作を残した。
作品11-13撮影
---------------------------------------------------
伊藤武夫 Takeo Ito 1907-1978
1923年帝国キネマ小阪撮影所に入り、1925年には阪東妻三郎プロへ移籍してキャメラマンとしてデビューした。松竹下加茂撮影所を経由して1937年に東宝に入社する。戦後はリアリズムを基調とした画面作りが特徴的で、黒澤明監督の『酔いどれ天使』(1948年)のほか、新藤兼人監督に協力して『原爆の子』(1952年)や『縮図』(1953年)など近代映画協会の諸作品に意欲的に携わった。
作品14-16撮影
---------------------------------------------------
鈴木喜代治 Kiyoji Suzuki 1901-1989
ニュース映画の撮影を経て1934年に十字屋映画部に加入、顕微鏡の微速度撮影などを駆使しながら太田仁吉との二人三脚で優れた理科教材映画を生み出した。対象への愛情を感じさせる撮影術が評価され、戦後は再び太田とともに『いねの一生』(1950年)などの傑作に携わる。50年以上にわたって科学映画を追求した功績により、没後、科学映像の撮影者を対象とする「鈴木賞」が設けられた。
作品17撮影
---------------------------------------------------
藤井春美 Harumi Fujii 1905-1980
1923年に東亜キネマに入社、マキノプロに移籍後、1928年には嵐寛寿郎プロの設立に参加して『抱寝の長脇差』(1932年)などで山中貞雄監督の右腕となる。マキノトーキーを経て1939年には満州映画協会に移り、引揚げ後は東映京都撮影所や宝塚映画などで活躍した。後進の育成にも力を注ぎ、関西の映画界で多くの技術者を育てたことで知られる。
作品18-19撮影
---------------------------------------------------
川崎新太郎 Shintaro Kawasaki 1907-1983
本名は常次郎。1925年帝国キネマに入社、阪東妻三郎プロ、新興キネマ(後に大映京都)を経て、1949年に東横映画(後に東映京都)に入る。時代劇に定評があり、東映ではとりわけ松田定次監督の右腕として活躍した。日本初の色彩シネマスコープ(東映スコープ)作品となった松田監督の『鳳城の花嫁』(1957年)を手がけたことでも知られる。
作品20-22撮影
---------------------------------------------------
松井鴻 Ko Matsui 1905-没年不詳
帝国キネマ小阪撮影所に入社後、市川右太衛門プロに移籍して1927年にデビュー、その後大都映画でも低予算の時代劇などを次々に発表した。戦後はマキノプロを経て東映京都撮影所に在籍、佐々木康、河野寿一といった監督たちのもとで優れた職人性を発揮し、時代劇を量産した。
作品23-24撮影
---------------------------------------------------
永塚一栄 Kazue Nagatsuka 1906-1982
1923年日活向島撮影所に入社、戦後は一時東映東京撮影所に属したが、日活の製作再開とともに復社、アクション映画を多数担当した。とりわけ野口博志・鈴木清順の両監督から厚い信頼を受けて、日活撮影所の重鎮キャメラマンの一人となる。最晩年に『ツィゴイネルワイゼン』(1980年)で清順映画に復帰、さらに翌年『陽炎座』を残して逝去、半世紀以上を現役キャメラマンとして活躍した。
作品25-27撮影
---------------------------------------------------
玉井正夫 Masao Tamai 1908-1997
1924年に帝国キネマ小阪撮影所に入り、1928年に市川右太衛門プロでデビュー。1936年にJ.O.スタジオ(後に東宝京都)に転じて東宝の看板撮影監督の一人となった。1951年の『めし』以来成瀬巳喜男監督の現場を支え、『浮雲』(1955年)、『流れる』(1956年)など映画史上の傑作を残したほか、『ゴジラ』(1954年)など東宝砧撮影所のエポックメイキングな作品にも多く名を残した。
作品28-30撮影
---------------------------------------------------
平野好美 Yoshimi Hirano 生没年不詳
東亜キネマで撮影技師として一本立ちした後、宝塚キネマ、今井映画を経由して1938年東宝に入社。榎本健一主演の音楽喜劇など娯楽作品を得意とし、戦後の新東宝でも喜劇や歌謡映画に力量を発揮した。その後溝口健二監督の『西鶴一代女』(1952年)に起用され、新東宝では中川信夫監督にも重用されて『怪談累が渕』(1957年)などの秀作を送り出した。
作品31-33撮影
---------------------------------------------------
高橋通夫 Michio Takahashi 1905-1993
1923年に松竹蒲田撮影所に入社、1930年にデビューする。トーキー以降は、メロドラマ『愛染かつら』(1938年)を始めとする野村浩将監督のヒット路線を担当、松竹大船撮影所の屋台骨を支えた。その後大映東京撮影所を代表するキャメラマンとして活躍し、アラン・レネ監督の日仏合作映画『二十四時間の情事』(1959年)でサシャ・ヴィエルニーと共同撮影を行った実績でも名高い。
作品34-36撮影
---------------------------------------------------
安本淳 Jun Yasumoto 1907-1990
1930年、日活太秦撮影所でデビュー、山中貞雄監督の『丹下左膳餘話 百萬両の壺』(1935年)をはじめとする時代劇に盛んに携わり、1937年に東宝に転籍する。戦後は稲垣浩、豊田四郎といった巨匠たちの右腕として信頼を受け、中でも『放浪記』(1962年)や『乱れる』(1964年)など、成瀬巳喜男監督の後期の傑作を支えたことで知られる。
作品37-39撮影
---------------------------------------------------
三木茂 Shigeru Miki 1905-1978
1922年国活巣鴨に入社、枝正義郎のもと各撮影所で修業を積み1926年にデビュー。流麗なキャメラワーク、ハイ・トーンの画調が支持されて溝口健二の『瀧の白糸』(1933年)や、阿部豊、伊丹万作ら気鋭の監督に起用された。日食の観察記録『黒い太陽』(1936年)でノンフィクションに開眼、亀井文夫の傑作『戦ふ兵隊』(1938年撮影)を残した。戦後は三木映画社を設立して教育映画の製作に専念した。
作品40-41撮影
---------------------------------------------------
小原譲治 Joji Ohara 1905-没年不詳
1924年に松竹蒲田撮影所に入り、1927年に撮影技師に昇進したが、初期は明るい軟調のトーンに定評があり、水谷文次郎や三浦光雄らとともに「蒲田調」のモダンな撮影を形作った。ほとんどの作品が現代劇であり、特に『伊豆の踊子』(1933年)など五所平之助監督とのコンビネーションが高く評価された。1947年に東宝から新東宝に移籍、その後1968年の引退まで大映東京撮影所で活躍した。
作品42-44撮影
---------------------------------------------------
中井朝一 Asakazu Nakai 1901-1988
塚越成治、三木稔らに師事し、1932年に新興キネマで撮影技師に昇進、1941年に東宝撮影所に移る。その評価を決定づけたのは『生きる』(1952年)、『七人の侍』(1954年)といったリアリスティックな画調による黒澤明監督の世界的な諸作品だが、抒情的なトーンにも定評があり、吉村公三郎の『偽れる盛装』(1951年)は「彼の美的フォトグラフィの頂点」(玉井正夫)とも評された。
作品45-47撮影